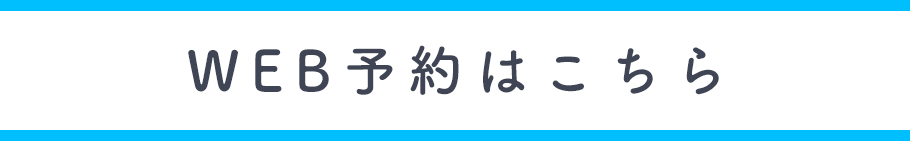#看護師コラム
第7回 夏の紫外線対策☀
☀紫外線のおはなし
肌に影響を与える紫外線には主に2つ
①肌の奥(真皮)に届き、シミやたるみの原因となる紫外線A派(UVA)
②皮膚の表面に炎症を起こす紫外線B派(UVB)
皮膚や眼に有害で皮膚がんリスクにもなる
🦴紫外線とビタミンDのつながり
ビタミンDは骨や歯の形成に重要な働きをしている
🦴🦷 供給源は日光浴+食事!
紫外線予防でビタミンD不足の妊婦が増加し、骨量の少ない赤ちゃんが増加
+
完全母乳栄養やアトピー性皮膚炎に対する除去食、生後の日光浴不足
⇓
乳幼児ビタミンD欠乏症の増加
将来、骨軟化症や骨粗鬆症になるリスクも↑
⚡ビタミンD合成に日光浴は大切だが、浴びすぎも有害となる⚡
Q.どのくらい日光に浴びていいの?
環境省によると関東地域(5-8月)で長袖・長ズボン着用で10分以上30分以下
12-2月は40分以上2時間以下がおすすめと言われています。
*ガラス窓の中では光を浴びてもビタミンD合成はされません
第6回 おむつかぶれのケア
ケアのポイント①
◎重要なのは擦らないこと!
汚染したらぬるま湯でやさしく洗い流す
おしりを拭くときには優しく押さえるように拭く
尿や便を完全に拭き取ろうとしないことが大切です
ポイント②
◎皮膚を保護する
ワセリンや亜鉛華単軟膏*は分厚めに手に取り、皮膚にそっとのせる(ケーキのアイシングのように)
*亜鉛華単軟膏:皮膚のバリア作用、余分な水分を吸い取る作用、消炎作用があります
*汚染した場合
目に見える汚れのみを取り除き、上から重ね塗りします
亜鉛化軟膏を無理に落とそうとすると摩擦によって悪化することがあるので気を付けましょう
ポイント③
◎清潔に保ち、乾燥させる
汚染したおむつはすぐ交換します
数分間だけでもいいので空気にさらす時間をつくり、乾燥させます
吸収性の高いおむつを使用するのも有効です
第5回 おむつかぶれ
繰り返すおしりの赤み…困っていませんか?
主な原因
・摩擦、湿気
・尿や便の化学刺激
・微生物の関与(カンジダなど)
・スキンケアや食事の影響
おむつかぶれのリスクが高まる時期
◎生後1~2カ月頃~2歳頃
・皮膚バリア機能が未熟
・離乳食の開始や食べ物の種類の変化で便の性質が変化
控えたほうが良い食品 🍊🍅
・酸性の強い食品(柑橘類、トマトなど)は肛門周囲の皮膚の 刺激につながります
・牛乳やヨーグルトなど乳製品等は乳糖不耐症がある場合、
軟便や下痢を誘発してしまいます🥛
・甘いジュースやお菓子などを摂りすぎると下痢や軟便を起こすことがあります
第4回 これって受診するべき?悩んだら症状をチェックしてみましょう!
【鼻水・鼻づまりの受診の目安チェックリスト】
☐ 呼吸が苦しそう(ゼーゼー・ヒューヒュー音がする)
☐ 鼻づまりでよく眠れない・夜に何度も起きる
☐ ミルクや食事がうまくとれない(飲み込めない・むせる) 、おしっこが少ない
☐ 耳を痛がる・しきりに耳を触る
☐ 鼻水が 5日以上続いている
☐ 鼻水が黄色〜緑色で粘りがある又は強いにおいがある
☐ 鼻水+発熱(38.5℃以上)がある
☐ ぐったりしている・機嫌が悪い
☐ 吸引後に毎回鼻血が出る・出血が続く
☐ 自宅で吸引・点鼻してもまったく改善しない
☐ 周囲に感染症が流行っている(RSウイルス、インフル、コロナなど)
受診の際に知りたいこと❢
いつから?どんな症状があるのか?
熱、咳、食欲の有無、鼻水(色・量・におい)など
兄弟や保育園、家族など周囲の感染状況も大切な情報になります!
第3回 吸引器に付属しているシリコンチップはどうやって選択したらいい❓
◆先端が丸く短いタイプのシリコンチップ
・奥に入りすぎにくく、安全性が高い
・鼻の入り口にフィットしやすい・粘膜を傷つけにくい
・ 乳児・0歳児、鼻の穴が小さい子、吸引に慣れていない家庭向け
◆ストレート に近く少し長さのあるシリコンチップ
・奥の鼻水にも届きやすい ・吸引効率が高い
・粘り気のある鼻水や奥の鼻水がとれにくいとき
・ 1歳以上の子どもに(鼻腔が広くなってくるため)
どのタイミングで吸引したらいい❓
・鼻が詰まっている、鼻水が垂れているとき
・起床後 夜間に溜まった鼻水を取り除きましょう
・授乳や食事の前 鼻が通ることで哺乳力・食事量がアップしやすくなります
・就寝前 夜間の鼻づまりや中途覚醒を減らすことができます
・お風呂後 湯気で鼻水がやわらかくなっていて、吸いやすくなります
・病院で点鼻薬や吸入薬・内服薬がある場合は基本的には鼻腔吸引をしてから薬剤投与が好 ましいと言われています
なぜ鼻腔吸引が先のほうがいいの❓
①吸引後に使用することで吸入薬や点鼻薬が届きやすくなり、薬の効果を高められる
② 内服後に吸引を実施すると嘔吐反射を起こしてしまうことがあります。もし先に内服し てしまった場合は15分程度おいてから実施しましょう
③吸引で呼吸が楽になり、内服しやすくなります
第2回 吸引器を使用した鼻水ケアについて
鼻腔吸引の目的は?
・呼吸困難の軽減 ・感染予防 ・鼻閉による哺乳困難や睡眠障害の改善
鼻腔吸引の方法
1. 手を清潔に洗い(石けん+流水)、 感染予防に努めます
2. 吸引器の準備・確認をします
電動タイプを使用する場合はチューブやノズルを正しく接続し、吸引圧がかかるか確認し
ます(圧力が設定できる吸引器の場合は6~10kpa:60~80mmhgを目安にします)
3. 子どもを安定した姿勢に整えます
・横抱きの場合は授乳の時の横抱きに近い姿勢で、頭は肘の内側にのせて支えます
・ 膝の上に座らせて行う場合は背もたれに寄りかからせ、頭がぐらつかないように支えます
4.鼻水が粘っているときは、吸引前に鼻用スプレーで湿らせ、1分ほど待ちます
5. 片方ずつ吸引を行います
ノズルをやさしく鼻の入り口にあてます
入れる長さは1〜1.5cm程度、 3〜5秒以内でやさしく吸います
角度はお顔に対して水平~やや下向きにいれます
*吸引していない側の鼻を軽く押さえる方法や吸引する鼻の横を指で軽く押し広げると吸いやすくなります
6. 終わったら鼻のまわりを清潔に拭きます
7.実施後は「安心・共感・ねぎらい」の声かけをこどもにかけてあげましょう
例:「がんばったね、えらいね」「お鼻すっきりしたね、楽になったね」「びっくりしたね、もうおしまいだよ」
子どもは自分の体の体感をうまく伝えることができません。体の体感を親や保育者が言葉にしてあげると理解が深まり、安心感につながります。
第1回 おうちでの鼻水ケア困っていませんか?
はじめに、鼻水の知識について!
鼻水は気道を保護するために加温・加湿の役割やホコリ・花粉・細菌・ウイルスなどをムチン(粘液)で絡めて、異物を排出させる役割があります。健康な人でも約0.5〜1ℓ程度生成されてると言われています。
なぜ鼻詰まりが起こるのか?
ウイルスやアレルゲンが鼻に侵入すると体が「異物」と認識することで鼻粘膜が刺激され、分泌の増加や浮腫を起こします。子どもは鼻腔が狭いため鼻詰まりを起こしやすいと言われています。
特に6歳以下は副鼻腔*の未発達、鼻腔が狭い、リンパ組織が大きくなることで副鼻腔や耳管の道がふさがれる、免疫力が未熟等の理由で副鼻腔炎を起こしやすいと言われています。
*副鼻腔とは?
鼻のまわりにある空気の入った小さいお部屋のような場所で、風邪やアレルギーがあるとこの場所に鼻水が溜まります。
鼻腔吸引が必要な年齢は?
0〜1歳は主に鼻呼吸で呼吸をしています。痰や鼻水が喉の奥に落ちてしまい、呼吸がしにくくなることもあるため吸引をして呼吸を楽にしてあげましょう。鼻をかむ動作ができるようになるのは一般的に3歳以降と言われています。 鼻水を自分で出せるようになるまでは吸引や拭き取りをしてあげましょう。